はじめに
現代では「薄毛=コンプレックス」とされることが多いですが、江戸時代を振り返ると事情は少し違っていました。当時は武士の象徴である「月代(さかやき)」という髪型が一般的で、頭頂部を剃るのが当たり前。つまり、現代でいう“ハゲスタイル”がむしろ格式あるものとして受け入れられていたのです。
しかし、自然に進行する薄毛=今でいうAGAの悩みが全くなかったわけではありません。むしろ、月代文化の中でこそ「隠せないハゲ」が浮き彫りになっていた可能性も…。
今回は、江戸時代におけるハゲ事情をユーモアも交えながら掘り下げていきます。
江戸時代の定番ヘアスタイル「月代」
江戸時代の男性にとって「月代」は身だしなみの基本。武士だけでなく、町人や農民も広く取り入れていました。
- 頭頂部を剃り上げ、残った髪を後ろで結ぶスタイル
- 武士にとっては忠誠心や礼儀の象徴
- かつ、夏の蒸し暑さを和らげる実用性もあった
現代人から見れば「わざわざ頭頂部をハゲにしている」ように映りますが、当時は社会的ステータスの一部。つまり江戸時代では「ハゲること」が恥ずかしいのではなく、「月代にしていないこと」が非常識とされていたのです。
自然なハゲ vs 人工のハゲ
ただし、月代はあくまで人工的に剃るもの。自然に薄毛が進んでいる人にとっては、剃った部分と自分のAGAの境目が曖昧になり、「どこまでが月代なのか」が分からない状況が生まれました。
「お前の月代、ちょっと広すぎないか?」
そんな冗談交じりの会話が交わされていた可能性もあります。
逆に言えば、当時の月代スタイルはAGAをカモフラージュする最適な髪型だったとも言えます。今の時代に「スキンヘッドで堂々とする」のと同じで、「剃ってるんだかハゲてるんだか分からない」状態がむしろ自然に受け入れられていたのかもしれません。
カツラ文化の発展
江戸時代にはすでに「カツラ文化」が存在しました。特に歌舞伎役者や武士の正装に欠かせないもので、役柄や身分を示すシンボルでもありました。
面白いのは、当時の富裕層や役者の中には、自然な薄毛を隠す目的でカツラを使っていた人もいたとされる点です。江戸時代の浮世絵や記録を見ると、髪がフサフサに描かれている人物が多いのですが、実際は「カツラでボリュームアップ」していた可能性も大いにあります。
つまり、現代の「増毛スプレー」や「医療用ウィッグ」のルーツは江戸時代にあったのです。
庶民のハゲ観
では庶民はハゲをどう見ていたのでしょうか。江戸時代の川柳や浮世絵には「ハゲネタ」が多数登場しています。
- 「ハゲ頭に雪が積もる」 → 冬の光景をユーモラスに描写
- 「ハゲても徳あり」 → ハゲを“長寿や智慧”の象徴とする考え方
一方で、子供が「おじさんハゲてる!」と笑いながら指差す場面も浮世絵に描かれており、今と変わらずからかわれる対象でもあったようです。
つまり江戸時代のハゲは「笑い」と「尊敬」の両方を受け止める存在。今の私たちにも通じる、複雑で人間味のある扱いをされていたのです。
もし江戸時代にAGA治療があったら?
ここからは少し妄想を。もし江戸時代に現代のAGA治療があったら、武士たちはどんなふうに使ったのでしょうか。
- ミノキシジル入りの髪油を毎晩塗る侍
- 戦の合間に「発毛茶」を飲む大名
- 「発毛の心得十カ条」を家訓にする藩主
なんだか想像するとクスッと笑えますよね。
「武士道と発毛道は両立するのか」――そんな新たな哲学が生まれていたかもしれません。
内部リンクでさらに学ぶ
現代の私たちは、江戸時代とは比べものにならないほど治療法が進化しています。もし本気で対策を考えるなら、以下の記事もチェックしてみてください。
まとめ
江戸時代の「月代文化」は、今でいうハゲをむしろ格式あるスタイルとして受け入れていました。とはいえ、自然に進む薄毛に悩んだ人がいたのもまた事実。カツラや川柳に残る痕跡から、当時も「薄毛との向き合い方」は存在していたことがわかります。
結局のところ、人々が薄毛に抱く感情は時代を超えて共通しています。深刻になりすぎず、ユーモアを交えて前向きに向き合う――それが、現代の私たちにとっても大切な姿勢なのではないでしょうか。
ほかにも面白い情報ありますので同カテゴリーの記事もご覧ください記事を見る⇒AGA面白情報一覧

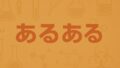

コメント